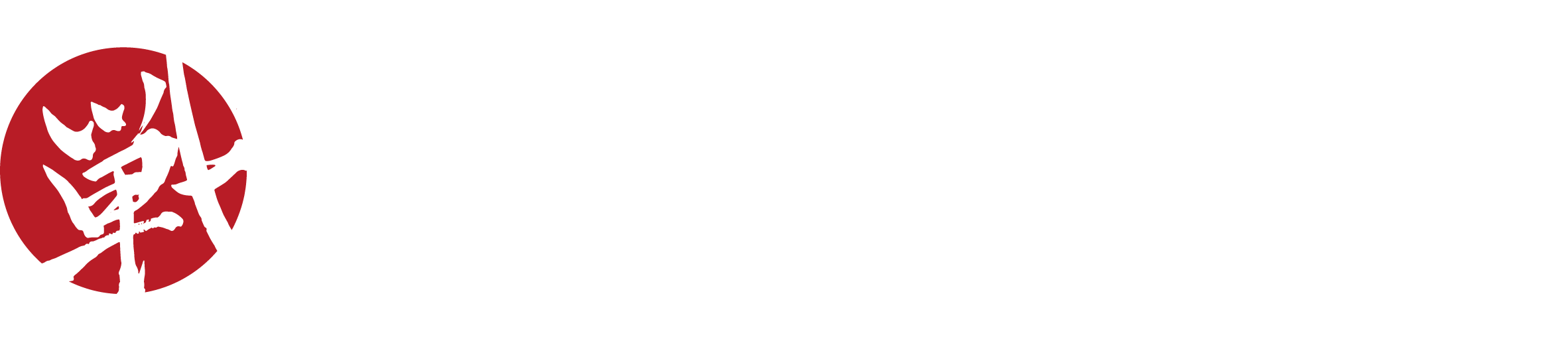江戸時代はどうやって夏の暑さをしのいでたの?暑さ対策ベスト5
こんにちは、ゼロワン大阪のしょーじです。
先日ゼロワンメンバーと祇園祭へ行ってきました。
普段は京都にいることが多いので、祇園祭の時期になると「今年も夏がやってきたな」と感じます。
そして先日、関西地方の梅雨明けが発表され、早くも猛暑日(最高気温35度以上の日)が続いています。
いよいよ本格的な夏がはじまりましたね。
冬より夏が好きなしょーじとしては、これからの数ヶ月がとても楽しみなのですが……
それにしても暑くないですか!?
去年こんなに暑かったかな? と思うくらいの気温と日差しの強さ。
まだ夏ははじまったばかりですが、少しバテ気味です。
外を歩いていても暑さに耐えられずコンビニで涼んで、
ついでにアイスやドリンクなど、冷たいものを飲んだり食べたりしてしまいます。
暑いなー、暑いなーと思いながら過ごしている中でふと思ったことが……
「昔の人はどうやって暑さをしのいでたんやろう?」
地球温暖化がヤバイ! と物心がついたときから聞いて育ってきたので、
きっと今のほうが気温は高いはずですが、
チャンバラ合戦 -戦 IKUSA-で触れる機会が多い、
戦国時代や江戸時代も夏は暑かったはず。
そこで、いくつかの資料が見つかった江戸時代の夏に注目して、
江戸に暮らす庶民がどうやって夏の暑さをしのいでいたのか、
しょーじの独断と偏見に満ちたランキング形式でご紹介します。
また最後には、小学生の自由研究・工作に役立つ考え方と情報をお届けします。
目次
第5位:目で見て涼を感じられるあの魚
江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキング第5位は、
「金魚の鑑賞」

金魚の鑑賞がはじまったのは江戸時代の後期だそうで、夏限定でたらいに金魚を入れて売り歩く商人がいたとか。
夏祭りの金魚すくいで獲った金魚はビニール袋に入れて持ち帰りますが、当時はそんなものありません。
そこで使用されたのが「金魚玉」と呼ばれるガラス製の球体容器。
金魚玉に金魚を入れて持ち帰り、そのまま軒下などに吊るして楽しみながら涼を感じていたそうです。
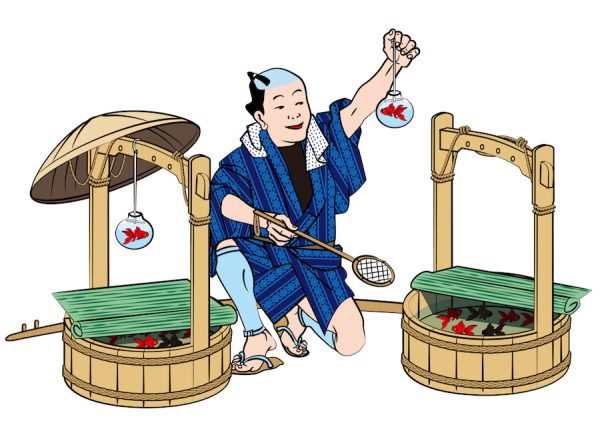
しかし、金魚で涼を感じるのはなにも江戸時代だけの話ではありません。
これまで累計で730万人が来場したアートアクアリウムイベントの主役も金魚なのです。
全国各地で開催されたため、目にした方も多いのではないでしょうか?
第4位:冬のイメージが強い温かくて甘いあの飲み物
江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキング第4位は、
「甘酒を飲むこと」
江戸時代の夏定番の飲み物といえば温かい甘酒。
冬の飲み物というイメージがありますが、「飲む点滴」ともいわれるほど栄養豊富な甘酒を
江戸っ子たちは夏バテ防止、疲労回復の栄養ドリンクとして飲んでいました。
その習慣からか、俳句の世界でも「甘酒」は夏の季語になっています。
小林一茶や与謝蕪村などが、甘酒の季語を使った俳句を詠んだ記録が残っています。
夏の時期になると、甘酒売りが江戸の街を歩き回り甘酒を売っていたそうです。
お値段は1杯4文(約100円)で、さながらスポーツドリンクのようなイメージでしょうか?
第3位:現代でもよく見る朝の光景
江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキング第3位は、
「打ち水をする」
江戸時代、多くの庶民が暮らしていたのは風通しの悪い長屋です。
どの長屋もいまでいう1Kの間取りで、狭いなかにさまざまな収納の知恵を用いて少しでも快適に過ごせるよう暮らしていたそうです。
風通しの悪い室内にこもっていても暑いため、太陽が沈んだ夕方からは外に出て打ち水をした上で、縁台を出して仕事後の時間を過ごしていたとか。
当時は道がアスファルトで舗装されていなかったので、打ち水をすると地面に水が染み込んでいったため、夕方以降なら道の表面温度が下がり、周りの空気も少し冷えたようです。
また、当時は夕方以降に外を出歩く人がほとんどいなかったので、道に縁台を広げて涼みながらおしゃべりしていても、他人の迷惑にならなかったとか。
現代の人通りが多いコンクリートジャングルに暮らす身としては、夕涼みにそんな時間を過ごせるのはとても贅沢なことのように感じます。
第2位:夏に欠かせないあの道具
江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキング第2位は、
「うちわを使う」
実はうちわの歴史は意外に古く、古墳時代(3世紀中頃〜7世紀で弥生時代と飛鳥時代の間)に中国から伝来したものだそうです。
しかし、この時代のうちわは、あおいで涼むよりも、貴族が威厳を保つ目的で顔を隠す際や、虫を追い払うために使われていたとか。
室町時代末期になると、現代のうちわに近いものが登場しました。
その後、江戸時代には庶民も手にできるものとして流通し、
涼むため・火をおこすため・虫を取るためなど日常生活のさまざまなシーンで幅広く使用されるようになりました。
うちわで有名な街が、香川県の丸亀市。
この地で作られる「丸亀うちわ」は、江戸時代の初期には製法が確立していたとされ、
金比羅参りのお土産として親しまれていたそうです。
こちらではうちわ作り体験ができるようなので、
丸亀市を訪れた際は、江戸時代に思いを馳せながらぜひ体験してみてください。
第1位:暑さをしのぐ手段の基本が堂々トップに!
江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキング第1位は、
「我慢」
「ここに来て我慢かよ!!」
と、肩透かしをくらった気分かもしれませんが、江戸時代の夏は暑くとも我慢するのが避暑の基本だったのです。
日中は用事や仕事がない限り、直射日光を避けて日陰でじっと耐えていたそう。
暑ければ長屋の出入り口を開けて少しでも風通しを良くすればいいのに、と思いましたが、
どうやら、そういうわけにもいかない事情があったようです。
「火事と喧嘩は江戸の華」と言われるほど、火事の多かった江戸の街。
そのため消化用の用水桶(火災に備えて水をためておく桶)や水路が多かったため、夏はそこから蚊が大量発生したそうです。
蚊取り線香が開発されたのは明治時代なので、江戸時代は杉や松の青葉を燃やして、その煙で蚊を追い払っていたとか。
規模は違いますが、松の青葉を燃やすとこのように大量の煙が発生します。
出入り口を開けてこの煙を我慢するのか、出入り口を閉じて暑さを我慢するのか、
まさに進むも地獄、退くも地獄状態ですね。。
きっと、江戸時代の庶民は暑さと煙に我慢しながら、夏の日々を過ごしていたのでしょう。
まとめ
独断と偏見に満ちた江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキングはいかがでしょうか?
普段生活をしていて思う素朴な疑問や不快なこと。
戦国時代や江戸時代に生きた人達も、同じ人間なのできっと似たような疑問や不快なことを感じていたはずです。
このようなちょっとした疑問や不快なことをきっかけに、時代をさかのぼって調べてみると案外おもしろかったりします。
これが歴史を知る楽しさのひとつなのかもしれませんね。
お子さんの自由研究を何にしようかと悩んでいるお父さん・お母さんは、
お子さんが感じる身近な疑問と時代の違いからアイデアを考えてみてもおもしろいかもしれませんよ!
以上、独断と偏見に満ちた江戸時代の庶民がしていた避暑方法ランキングでした!
【自由研究にピッタリ!】あなたのお子さんも90分で武士に!戦国ワークショップ-TERAKOYA-(8/19@京都)
武士の一日、、、
それは、髷(まげ)を結うところから始まる。
甲冑を自分で作成。仲間と息を合わせて弓の鍛錬。そして、刀を使っての実践修行。
そんな、武士が当時(たぶん!)やっていたことを、現代版ワークショップにアレンジ!
武士の一日を90分で模擬体験できる新感覚プログラム!
それが、『戦国ワークショップ-TERAKOYA-』
修行内容は以下の通り。
〈一〉髷を結う
〈二〉ダンボール甲冑制作
〈三〉弓矢の射的修行
〈四〉チャンバラ合戦-戦IKUSA-
心・技・体を鍛える楽しい修行をクリアし、一人前の武士を目指そう!
◆◇◆イベント概要◆◇◆
【日程】8月19日(土)
【場所】紫明会館(京都市北区小山南大野町1番地)
【時間】〈第一部〉11:00~12:30(受付 10:30~)
〈第二部〉12:30~14:00(受付 12:00~)
〈第三部〉14:00~15:30(受付 13:30~)
【対象】小学生 ※ご兄弟が小学生で参加する場合に限り未就学児の参加も可能です
【参加費】2,500円(髷材料費、段ボール甲冑キット代含む)
【参加方法】事前予約制 こちらのサイトよりお申込みください
【定員】各回先着30名
【持ち物】動きやすい服装、ダンボール甲冑の持ち帰り用袋、侍魂
【アクセス】地下鉄「鞍馬口駅」から徒歩10分
http://solecafe.jp/1999/01/post-250.html
◆◇◆プログラム◆◇◆
〈一〉髷を結う
布とヒモで、手作りの髷を結います。さぁ、武士に変身だ!
〈二〉ダンボール甲冑作り
特製のダンボールキットを組み立て装飾をし、好きな家紋を描き、自分だけのオリジナル甲冑を作ります!
〈三〉弓矢の射的修行
仲間と隊列を組み、的を狙い一斉発射。戦国時代、強力な武器だった弓矢の体験を行います!
〈四〉チャンバラ合戦-戦IKUSA-
スポンジの刀で相手の肩についた命(ボール)を落とし合う、全国で大人気の体験型戦国アクティビティを開催!
作った甲冑はお持ち帰りいただきます!
◇チャンバラ合戦-戦IKUSA-とは?
NPO法人ゼロワンが主催する世代を超えて楽しめる、全く新しい合戦型のアクティビティです!当たっても痛くないスポンジの刀を持ち、腕に命(カラーボール)を取り付けて、大人数で戦い、生き残った人数を競います。
◎チャンバラ合戦の基本ルール
一、まずは利き手で刀を持ちます。
二、次に反対側の腕に命(ボール)を装着します。
三、戦開始の合図で「オォー!」と雄叫びをあげ合戦を開始し、相手の命を落とします。
基本ルールはこれだけ!とっても簡単で、老若男女問わず、小さな子どもからお年寄りまで幅広く遊んでいただけます。
※注意事項※
●今回の戦中の事故や怪我については、自己責任となりますので予めご了承ください。
●当日撮影した写真は、戦のHPやFB等で使用させていただくことがございます。掲載されると困る方は、スタッフまでお声掛けください。
----------------------------
【Q&A】
●服装はどんなものがいいですか?
- 動きやすい格好でご参加ください。
●勝敗のつけ方は?
- 腕に取り付けた命(ボール)が落ちるとアウト!
●刀などはどんなものを使用していますか?
- 本物・・・ではありません(笑)
刀状の丈夫な風船を膨らませたもの、またはスポンジ刀を使用します。顔や腕にあたっても痛くないので安心してください。
●チャンバラ合戦 -戦IKUSA-とは?
-公式HPをご覧ください。https://tyanbara.org/
【主 催】 NPO法人ゼロワン 戦-IKUSA-事務局
【理 念】外遊びを再び日本の文化に
【設 立】 2013年12月
【運営サポート企業】 株式会社IKUSA(旧・株式会社TearsSwitch)
※ チャンバラ合戦-戦 IKUSA-はネットワークビジネス、宗教法人、営利団体とは全く関係がありません。それらの営業目的で来られることはご遠慮下さい。