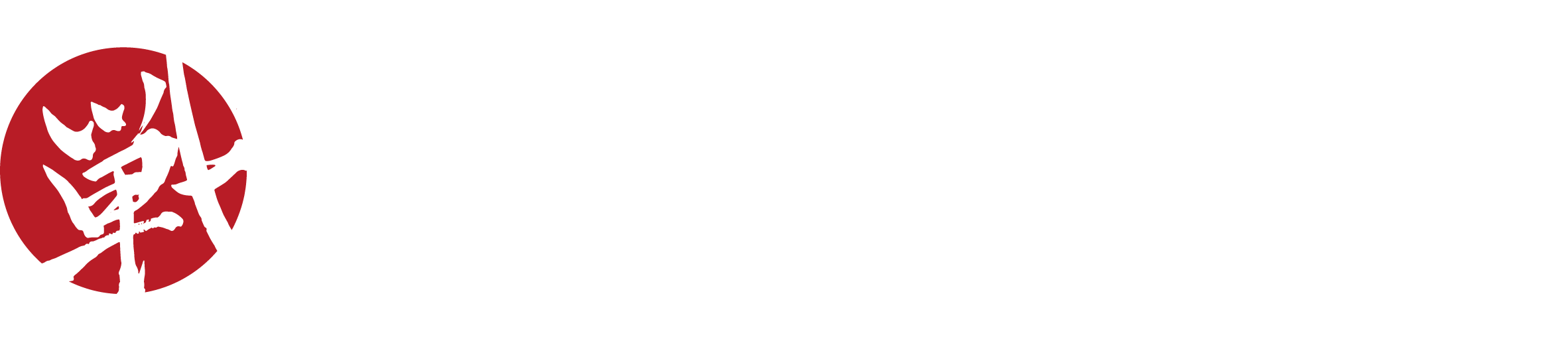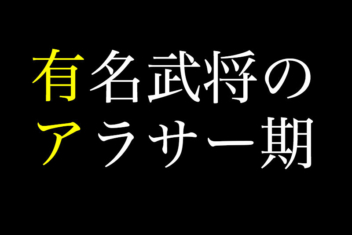あの戦国武将たちと「器」のカンケイを、チャンバラの歴女がお伝えするブログ。
はじめまして、チャンバラスタッフのせりーぬです。

ラグジュアリー・ブランドのCELINEを彷彿とさせるあだ名ですが、残念ながらまったく関係ありません。本名が「せり」なので、せりーぬです。
井上陽水の奥さまであり歌手の「石川セリ」の語感がいいから、という理由だけで名付けられました。なお、石川セリさんの代表曲は「ダンスは上手く踊れない」。ダウナーな雰囲気は、引き継いでいるはずです。
さて、チャンバラの運営をしていると、「さぞ歴史に詳しいんでしょう?」「戦国時代とかお好きなんでしょう?」と思わがちです。
でも実際は、そうでもありません。
どちらかというと、歴史とかよくわからない!楽しければオK!というパーティーピーポーが多いのが現実です。
一方、ダウナーに生まれた私としては、パリピのテンションにイマイチついていけません。
それこそ、歴史小説を読んで胸躍ったり、江戸東京博物館のジオラマに胸たぎったり。そんな人生を歩んできました。
なもんで、チャンバラスタッフの皆さんからは、「歴女」的な扱いをいただいています。
そんな私が、歴史以外にも持つダウナーな趣味が「器あつめ」。
なかでも好物なのが、日本の工芸品。とくに焼き物は、産地によってそれぞれ肌合いや色味などたくさんの個性があるので、集めがいがあります。
もちろんみるだけではなく、実際に食事につかうのがまた楽しい。同じ料理でも、器づかいで雰囲気が変わってきます。
お気に入りは、私の地元・栃木の「益子焼」。土を感じる肌目が、ほっこりする焼き物です。
毎年GWと11月上旬には、益子陶器市が開催されます。町中に陶器の露店が出て、見ているだけでも楽しいですよ。
最近は、買うだけでは飽き足らず、陶芸体験も!
↓ 自作の器です。
というわけで、 ここからは「器」と「歴史」についてのお話です。
毎日の食事に欠かせない器ですが、実は戦国時代の有名武将たちと深い関わりがあることをご存知でしょうか?
いくつか、代表的なものをご紹介します。
器の代表格「瀬戸物」。その立役者は織田信長?!
陶磁器全般を「瀬戸物」と呼ぶことがあります。しかし本来「瀬戸物」は、愛知県瀬戸市近辺でつくられる「瀬戸焼」のこと。
瀬戸の焼き物が有名すぎて、総称に使われるようになったんですね。ツナ缶全般を「シーチキン」と呼んでいるようなものです。
瀬戸焼にも、志野焼や織部焼など、いくつか種類があります。特に織部焼は、創始者・古田織部を主人公とした漫画「へうげもの」がヒットしたこともあり、近年人気を集めています。
個性的な色や柄を活かして、小鉢として取り入れれば、食卓のアクセントに!
☆商品詳細はこちら▶︎http://urx.red/z7Pi
そんな「瀬戸焼」を有名にしたのは、なんとあの織田信長なのです!
信長が茶の湯にハマっていたのは有名な話。戦の褒美に、土地ではなく茶器をあげたほど。(武将によっては不満だったようですが。。)
そんな信長は、瀬戸を焼き物の町として保護しました。その結果、職人が集まるようになり、今に続く一大名産地に育ったのです。
歴史上の人物・信長が、急に身近に感じられますね。
豊臣秀吉が誕生のきっかけをつくった!あの有名な器。
信長の家臣・秀吉もまた、器の歴史に重要な役割を果たしています。
それは、佐賀県の名産品「有田焼」。
伊万里焼とも言われるこの器は、薄く軽やかな仕上がりと、華やかな絵付けが特徴です。
華美な印象が強く、日常づかいのイメージはあまりない有田焼。でも、最近はシンプルでモダンなシリーズも出ています。
オススメはこの「JAPAN CHERRY」シリーズ。桜を思わせる淡いピンクが、料理をひきたててくれそうです。
☆商品詳細はこちら▶︎http://urx.red/z7Po
この有田焼、秀吉の朝鮮出兵がきっかけで生まれたと言われています。出兵の際、佐賀藩主の鍋島氏が朝鮮陶工たちを日本に連れてかえりました。そのうちの一人が、いい土を求めてたどり着いた土地が有田なのです。
そこから有田は焼き物の里として発展したのでした。
大河ドラマ「真田丸」でも、秀吉の衣装や部屋の内装から、その派手好みがよく伝わってきました。有田焼の絢爛豪華さと通じるものがありますね。
信長・秀吉ときたら、もちろんあの武将も…!
この流れなら当然、次の武将はそう、徳川家康!
彼もまた、ある器をひいきにしていました。当時、戦国武将にとって、茶の湯がいかに重要だったかわかりますね。
その器とは・・・「志戸呂焼」という焼き物!
☆商品詳細はこちら▶︎http://urx.red/z7Py
今も買うことができますが、瀬戸焼や有田焼と比べると知名度が低いせいか、あまり種類はないようです。
見た目も、ちょっと素朴な感じ^^
三種類の器を比較すると、3人の武将の性格や好みが伝わってくるようですね。
いま当たり前のように使っている器。日本各地に産地がありますが、そこには日本の歴史がつながっているんです。
今回は陶器にしぼってご紹介しましたが、漆器や調理器具の産地も、実は歴史に関わりがある場所が多いです。
そう思うと、毎日の食卓も普段と違って見えてきますね。これを機に、ぜひ各地の器に注目してみてください!