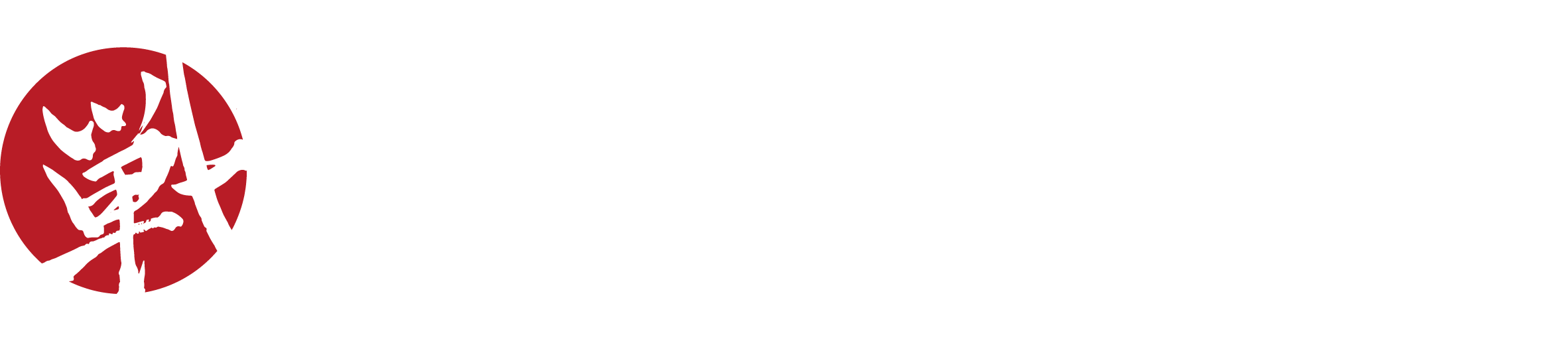武力で最強な戦国武将ランキングTOP5!織田信長や徳川家康を抑えたのは?

戦国時代は、群雄割拠の時代です。武将たちは知略を尽くして駆け引きを繰り広げ、しのぎを削りました。
そのようななかでも、理屈抜きに「強い!」と感じさせる武将がいます。知名度だけでは語れない、戦場での武勇や印象深い逸話から「本当に武力で最強なのは誰か?」を独断と偏見で真剣に考えてみました。織田信長や徳川家康といった有名な戦国大名をも凌駕する、戦場の英雄は誰なのでしょうか。
本記事では、武力で最強な戦国武将TOP5をランキング形式で紹介します。
※武将の名前は、時期に限らず統一して表記しています。
第1位:本多忠勝|生涯57戦無敗、まさに戦国最強の男

本多忠勝は、徳川家に仕えた戦国武将です。酒井忠次・榊原康政・井伊直政とともに「徳川四天王」と呼ばれ、徳川家康の側近として活躍しました。
数々の激戦に参戦しながら「生涯57戦してかすり傷ひとつなし」という逸話を持ちます。名槍「蜻蛉切」の使い手としても有名です。
織田信長からは「花も実も兼ね備えた武将だ」、武田軍の小杉左近からは「家康に過ぎたるものが二つあり、唐の頭に本多平八」と讃えられたとされています。多くの合戦で常に前線に立ち、敵味方を問わず武勇を称賛された忠勝は、戦国随一の猛将といえるでしょう。
以下、本多忠勝の活躍した戦いや逸話を見てみましょう。
姉川の戦い(1570年)
「姉川の戦い」は徳川・織田連合軍と浅井・朝倉連合軍が衝突した戦いです。織田・徳川連合軍は当初、撤退寸前まで追い込まれました。しかし、突破口を開くため、忠勝は単騎で朝倉軍に突入します。これを見た徳川軍は忠勝を討たせてはならないと奮起し、朝倉軍の陣形を崩すことに成功しました。
またこの戦いにおいて忠勝は、朝倉軍の豪傑であり「太郎太刀」という大太刀使いの真柄直隆と一騎討ちを行い、勇名を馳せました。
一言坂の戦い(1572年)
「一言坂の戦い」は、徳川家康と武田信玄が衝突した戦いです。信玄からの侵攻に対して、本多忠勝は偵察隊として先行していました。そこで武田の先発軍と遭遇し、戦が始まってしまいます。偵察隊を撤退させるため、忠勝は殿(しんがり)をつとめ、坂の下という不利な地形に陣取ります。
その際、忠勝は武田四天王の1人で「不死身の鬼美濃」と呼ばれた馬場信春に追撃されますが、無事に振り切ります。その活躍に支えられ、家康は浜松城への退却に成功しました。
三方ヶ原の戦い(1573年)
「三方ヶ原の戦い」は、徳川家康・織田信長が武田信玄と対峙し、大敗を喫した合戦です。この戦いで本多忠勝は、家康の命を守るために獅子奮迅の働きを見せました。徳川軍は壊滅的な打撃を受けますが、忠勝は僅かな兵で追撃する武田軍を必死に食い止めます。家康を無事に退却させた功績は極めて大きいものでした。
関ヶ原の戦い(1600年)
「関ヶ原の戦い」で、本多忠勝は徳川家康率いる東軍の最高司令官にあたる「軍監」をつとめました。
戦いの終盤、西軍は総崩れとなりました。東軍に囲まれた薩摩(現在の鹿児島県)の島津義弘は、決死の「敵中突破」を敢行します。島津軍を見逃す武将もいましたが、忠勝は軍のなかに切り込み、大きな痛手を与えたと言われています。また、島津軍の放った鉄砲玉が忠勝の馬にあたって死んでしまいますが、家臣の差し出した馬に乗り換えて戦い続けたとされています。
忠勝は90もの首級を挙げ、この活躍により、伊勢桑名(現在の三重県桑名市)10万石を与えられました。
第2位:立花宗茂|「東の本多忠勝、西の立花宗茂」
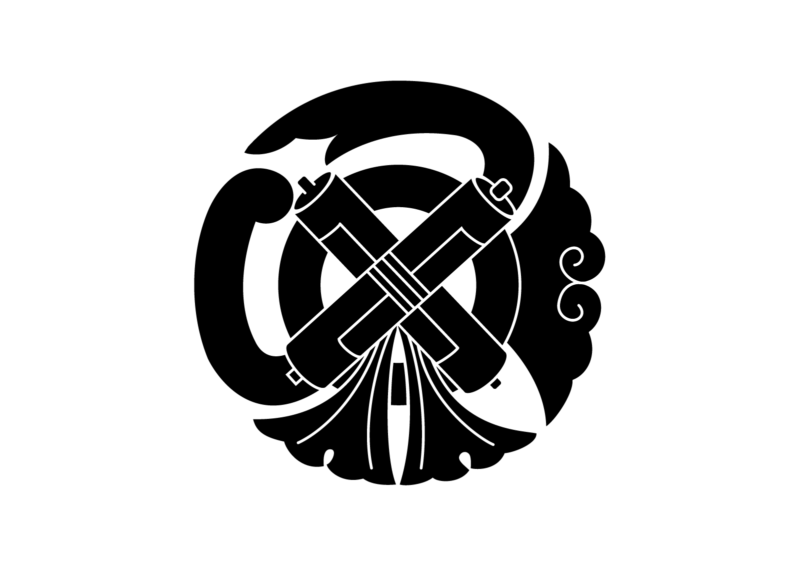 立花家の家紋「祇園守紋」
立花家の家紋「祇園守紋」
立花宗茂は、主に九州で活躍した戦国武将です。豊臣秀吉に「東の本多忠勝、西の立花宗茂、東西無双」と称されるほどの武勇を誇りました。
宗茂は、豊後国(現在の大分県)を本拠地とした大友家の家臣・高橋紹運の長男として生まれます。その後、同じく大友家の家臣である立花道雪に請われて養子となりました。宗茂は2人の父の勇猛さを受け継ぎ、数々の合戦で活躍します。さらに、生涯で一度も戦に敗れなかったという伝説を残しています。
「関ヶ原の戦い」では西軍につき所領を没収されますが、その人望と武勇が徳川家康に高く評価され、旧領回復を許されます。これは異例のことで、宗茂の実力と人格の高さが偲ばれます。
立花山城の戦い(1586年)
「立花山城の戦い」は、大友家と島津家の戦いです。九州統一を目指す島津軍が、宗茂の守る立花山城に進軍しました。島津軍はこの戦の前に、「岩屋城の戦い」で宗茂の実父・高橋紹運を討ち取っていました。
島津軍が約3万の大軍で城を包囲したのに対して、宗茂はわずか3,000の兵で籠城しました。圧倒的な兵力差にもかかわらず、立花軍は徹底抗戦を続け、豊臣秀吉の援軍が到着するまで持ちこたえました。
その後、宗茂は撤退する島津軍を追い上げ、その勢いで紹運が自害した岩屋城を奪還しています。
九州攻め(1586年〜1587年)
「九州攻め」は、豊臣秀吉と、島津軍をはじめとした九州諸将との戦いの総称です。この戦いで立花宗茂は、豊臣方として活躍します。
宗茂は、肥後国(現在の熊本県)の竹迫城や宇土城・出水城を攻め落としました。また島津方から人質をとるといった動きも見せます。その働きの甲斐もあり、島津家は降伏し、秀吉は九州攻めを成功させます。
秀吉は宗茂を高く評価し、筑後国柳川8万石を与え、大友氏の家臣から大名へと取り立てました。
文禄の役(1592〜1593年)
「文禄の役」は、豊臣秀吉が行った朝鮮出兵のうち最初の戦いです。宗茂は、小早川隆景の指揮下で戦い、特に「東萊城」の攻略では大きな活躍を見せました。
その奮闘はすさまじく、刀が歪んで鞘に収まらなくなったと言われています。秀吉からは「日本無双の勇将たるべし」との書状が送られ、俸禄は13万石余りに加増しました。
関ヶ原の戦い(1600年)
秀吉の死後、「関ヶ原の戦い」において立花宗茂は西軍に属します。徳川家康から東軍につくように誘われていましたが、秀吉への忠義を貫きました。
関ヶ原の戦いの前哨戦となる「大津城の戦い」で、宗茂は養父である立花道雪の発案した「早込」を用い、激しい銃撃を行いました。その勢いで相手を降伏に追い込みます。
しかしこの戦いのために、宗茂は本戦には間に合いませんでした。総大将の毛利輝元に徹底抗戦を説きますが、受け入れられなかったことから、自領の柳川に戻ります。柳川では黒田孝高(如水)・加藤清正・鍋島直茂に攻められ、奮闘するものの、説得により降伏しました。
この後、宗茂は浪人になりますが、家康に取り立てられて大名へと復帰します。さらに「大坂の陣」では戦の動向について予想を的中させるなどして徳川方に貢献し、旧領に復帰を果たしました。関ヶ原の戦いで西軍についた武将のうち、旧領を回復したのは宗茂のみです。
第3位:高橋紹運|たった700で数万の大軍に抗した「風神」
 高橋紹運の墓
高橋紹運の墓
高橋紹運は、立花宗茂の実父にして、大友家を支えた屈指の猛将です。同じく大友家の重臣であった立花道雪とともに「風神雷神」と称されました。
特に有名なのが1586年の「岩屋城の戦い」です。わずか約700人の兵で、島津軍2万の大軍を迎え撃ち、半月にわたり死闘を繰り広げました。
最終的には全滅するものの、その奮戦によって宗茂の守る立花城や大友領の防衛に大きく貢献したとされています。敵である島津軍の武将もその勇敢さに心を打たれ、紹運の死を悼みました。
筑後遠征(1584年)
「筑後遠征」とは、高橋紹運と立花道雪が、大友義統の出兵要請を受けて、1日で筑前(現在の福岡県北部)から筑後(福岡県南部)まで向かった遠征です。
当時の筑前・筑後・肥前(現在の佐賀県・長崎県)では、大友氏の支配が揺らぎ、反乱が相次いでいました。そのようななかで、大友氏を攻めていた肥前の龍造寺氏が、島津軍に敗れる「沖田畷の戦い」が起きます。これを好機と見た大友氏の命で、紹運と道雪は出陣しました。
紹運は筑後の諸城を次々と攻略し、離反した勢力を討伐または服従させました。しかし、不幸にも道中で盟友・道雪が病死してしまいます。これをきっかけに筑前の宝満城を敵に奪われたことから、紹運は筑前に戻り、城を奪回しました。
岩屋城の戦い(1586年)
「岩屋城の戦い」は、高橋紹運が島津氏の攻撃を受けた戦いです。当時、島津氏は九州制覇を目指して九州北部へ進攻していました。紹運はわずか763名の兵を率いて岩屋城に籠城し、2万とも言われる島津軍を迎え撃ちました。
圧倒的な兵力差にもかかわらず、紹運は兵を巧みに指揮し、半月にもわたって徹底抗戦を続けました。最後、紹運は高櫓に登って壮絶な割腹をしたとされています。
この奮戦により、島津氏は大きな痛手を追いました。紹運の死闘は、島津氏に九州統一の野望を諦めさせる一因となりました。
第4位:島津義弘|「鬼島津」の異名を持つ猛将

島津義弘は、薩摩国の武将で、第16代当主・島津義久の弟です。戦国時代屈指の猛将として「鬼島津」の異名で恐れられました。
特にその武勇が際立ったのが「関ヶ原の戦い」です。西軍が敗北するなか、義弘はわずかな手勢で敵中突破を敢行し、徳川本陣を突き抜けて薩摩へ撤退しました。その壮絶な脱出劇は「島津の退き口」として語り継がれ、敵味方を問わず驚嘆させました。
また、「文禄の役」「慶長の役」では朝鮮半島で戦果を挙げ、島津軍の強さを天下に知らしめました。
木崎原の戦い(1572年)
「木崎原の戦い」は、島津義弘と日向国(現在の宮崎県)の伊東義祐のあいだで行われた戦いです。「覚頭合戦」とも呼ばれています。
伊東義祐が約3,000の兵を投入したのに対して、島津義弘は300人足らずの手勢でした。しかし義弘は少数の兵を多く見せて伊東軍を攻撃し、退却させます。義弘は伊東軍が休憩しているところを切り込み、大将の1人伊東祐信と一騎打ちをして討ち取ります。
さらに、退却すると見せかけて、追撃してきた敵に反撃する戦術「釣り野伏せ」を用い、伊東軍に壊滅的な打撃を加えました。この勝利により、島津家は南九州を制圧しました。
戸次川の戦い(1587年)
「戸次川の戦い」は、豊臣秀吉の「九州攻め」における戦いで、島津勢と長宗我部元親・信親父子など豊臣勢のあいだで行なわれました。
ここでも義弘は得意の「釣り野伏せ」により豊臣勢を誘い込み攻撃します。豊臣勢は大混乱に陥り、長宗我部信親が討死するなど大損害を被りました。この勝利により島津軍は豊後を制圧し、九州統一に大きく前進します。
文禄・慶長の役(1592〜1598年)
島津義弘は「文禄の役」「慶長の役」において、それぞれ朝鮮にわたり参戦しました。
慶長の役では、藤堂高虎らの水軍と連携して、朝鮮水軍を挟み撃ちにして将軍を討ち取りました。また「泗川の戦い」では、わずか7,000の兵を率い、明・朝鮮の20万人の大軍(諸説あり)を打ち破り、徳川家康に「前代未聞の大勝利」だと評価されます。
秀吉が病気で亡くなり撤退戦になっても、義弘は戦績をあげています。その戦いぶりは明・朝鮮軍を恐れさせ、「鬼石曼子(グイシーマンズ)」つまり「鬼島津」と称されたと言われています。
関ヶ原の戦い(1600年)
「関ヶ原の戦い」において、島津義弘は西軍につきました。義弘は大軍を準備することができず、率いることができたのは1,000名余りの兵だったと言われています。(諸説あり)
関ヶ原の戦いでは、小早川秀秋が寝返ったことをきっかけに、西軍は総崩れとなります。その結果、島津軍は敵のなかで孤立してしまいます。義弘は切腹しようとしましたが、甥・豊久の説得により「敵中突破」を決行しました。
このとき島津軍は「捨て奸」という戦術を用いました。数名の足止め部隊が命をかけて敵を止め、それが全滅するとまた新しい部隊が残るという撤退方法です。この結果、豊久をはじめとする多くの兵が亡くなりましたが、義久は無事に本国に帰還することができました。生き残った兵は約80名だと言われています。
この撤退戦は「島津の退き口」と呼ばれ、敵味方双方に強い印象を与えました。
第5位:島津義久|島津家を率いた冷静沈着な大将

島津義久は、薩摩国の大名で、第16代当主です。家督を相続してから薩摩統一、そして薩摩・大隅・日向の三州統一を成し遂げました。
義久は、島津義弘・歳久・家久といった勇猛な弟たちを束ねた島津四兄弟の長兄としても知られています。幼い頃は大人しく、弟の義弘のほうが当主にふさわしいとの声もありましたが、祖父の島津忠良からは「義久は三州の総大将たるの材徳自ら備わり、義弘は雄武英略を以て傑出し」と、その素質を評価されていました。忠良の期待通り、義久は島津家を率いて躍進します。
数々の合戦を冷静な判断で勝利に導き、戦場はもちろん政治的にも有力武将と駆け引きを繰り広げて、動乱の世で家を守り抜いた武将です。
薩摩統一(1570年)
島津義久は、薩摩統一の立役者として重要な役割を果たしました。義久の父で第15代目当主の島津貴久は、「島津の英主」と讃えられ、内乱状態だった島津一族を統一します。しかし義久が家督を継いだ段階では、薩摩は有力国人が割拠し、島津家による支配は盤石ではありませんでした。
義久は弟たちを重臣として配置し、各地の反抗を次々と制圧し、島津家の権威を確立しました。特に3,000の伊東軍を300の島津軍が破った「木崎原の戦い」が有名です。この躍進は、のちの三州統一への足掛かりとなりました。
耳川の戦い(1578年)
「耳川の戦い」は、島津義久が大友氏と対決した合戦です。当時、大友宗麟は日向国奪還を目指して大軍を派遣しましたが、義久は奇襲や島津軍が得意とする戦術「釣り野伏せ」などを駆使して大友軍を翻弄し、勝利をおさめました。
この戦いにより大友氏の支配力は大きく後退し、島津氏が九州制覇に一歩踏み出すことになりました。
沖田畷の戦い(1584年)
「沖田畷の戦い」は、島津義久が九州統一を目指すなかで、肥前の有力者・龍造寺隆信を討った重要な合戦です。当時、大友氏は「耳川の戦い」で衰えてはいたものの油断はできず、義久は龍造寺軍を少数精鋭の兵力で迎え撃ちます。
龍造寺隆信は、兵力差があることで慢心していました。それに対して島津軍は策を講じ、湿地と深田のなかにあぜ道の通る「沖田畷」を戦場に選びます。戦いが始まってから、島津軍は撤退を装い、あぜ道に龍造寺軍を誘い込んだうえで、銃撃により反撃しました。
龍造寺軍は大混乱に陥り、隆信は戦死しました。この勝利で龍造寺氏の勢力は一気に衰退し、島津氏の北九州進出が現実のものとなりました。
まとめ

戦国時代には、数多くの武将が活躍しました。統率力や戦略・戦術の考案力、駆け引きのうまさ、経済力など、彼らの強さの理由はさまざまです。しかし、「武力」としての強さは見逃せない要素です。
この記事では、独断と偏見で、武力で最強な戦国武将TOP5を紹介しました。
ぜひこの記事を参考に、ご自身の考える最強武将ランキングをつくってみてはいかがでしょうか?