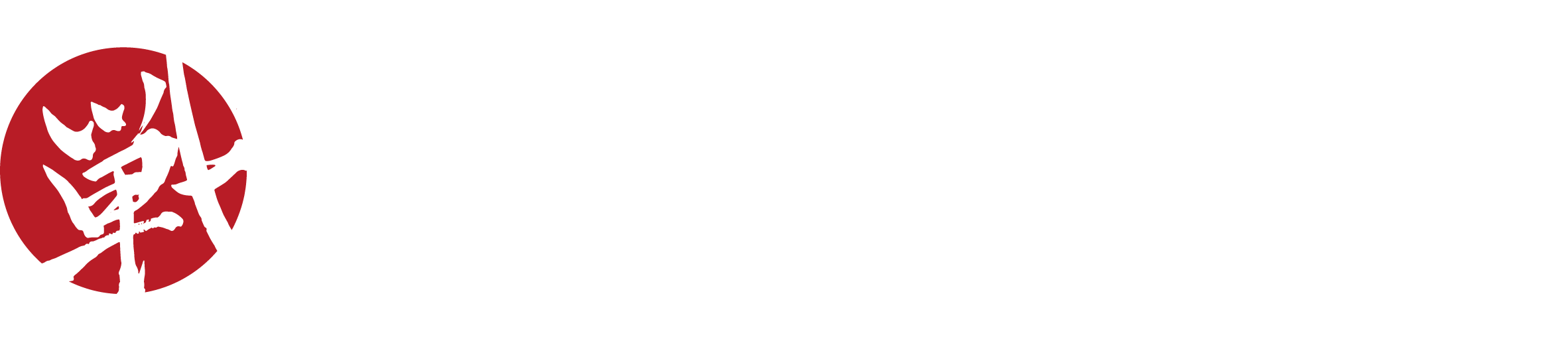戦国時代の武将たちは、数々の逸話を残しています。また、戦国時代の豆知識は、当時の人々を取り巻く事情を伝えてくれます。
そのような戦国武将の逸話・戦国時代の豆知識を知れば、戦国イベントに参加したり、歴史スポットを訪れたりすることをより楽しめます。
本記事では、戦国武将の逸話を知ると体験が楽しくなる理由、有名な戦国武将の逸話、戦国時代にまつわる豆知識、戦国時代を体験できるイベントや歴史スポット、戦国イベントを開催する予定の方におすすめの戦国アクティビティを紹介します。
戦国武将の逸話を知ると体験が楽しくなる理由

戦国武将の逸話や戦国時代の豆知識を知ると、戦国イベントや歴史スポット巡りをより楽しく体験できます。
例えば、武将の逸話を知ったうえで戦国イベントに行けば、どのような物語が再現されているのかを理解でき、没入感が得られるでしょう。また、その土地で繰り広げられた歴史を知ってから現地を訪れると、歴史の舞台が目の前に広がる感覚を味わえます。
知識を身につけることで、観光がより特別な体験に変わります。
有名な戦国武将の逸話7選

ここでは、有名な戦国武将の逸話を7つ紹介します。
1.織田信長「桶狭間の戦い」
「桶狭間の戦い」は、1560年に織田信長が今川義元を打ち破った合戦です。25,000人もの大軍を率いていた今川軍に対して、織田軍は2,000人〜3,000人であったとされています。また、今川家は足利将軍家の親族であり、東海地方最大の大名であったのに対して、織田家は領主に成り上がったばかりで、身分の差もありました。そのような状況にもかかわらず、格上の相手に勝利したこの戦は、信長の天下統一への道を開きました。
通説では、信長は地形を利用し奇襲を敢行して義元を討ち取ったとされていました。しかし近年の研究では、信長が今川軍を分散させ、義元の周辺が手薄になったときを見計らって攻撃したという説が出ています。
2.豊臣秀吉「墨俣一夜城の伝説」
「墨俣一夜城(すのまたいちやじょう)の伝説」とは、豊臣秀吉(当時は木下藤吉郎)が1566年に一夜で砦を築いたとされる伝説です。秀吉は、美濃の攻略を進める織田信長から、墨俣(現在の岐阜県大垣市)に城を築く任務を与えられます。それまで、信長の重臣・柴田勝家や佐久間信盛がこの任務に挑みましたが、敵の妨害により失敗してきました。しかし秀吉は、城の資材を川の上流から流し、墨俣で一気に組み立てることで、城を一晩で完成させました。この奇策により信長からの信頼を得た秀吉は、出世の足がかりをつかんだとされています。
この話には資料的な裏付けがなく、後世の創作だと言われていますが、秀吉の知略と行動力を象徴する物語として語り継がれています。
3.上杉謙信「敵に塩を送る」
「敵に塩を送る」は、越後国(現在の新潟県)の武将・上杉謙信の逸話です。戦国時代、謙信の宿敵である武田信玄は、今川氏とも対立していました。武田氏の領地は内陸であり、同盟国の駿河国(現在の静岡県)から食塩を輸入していましたが、今川氏の計略により、塩の供給を断たれ困窮していました。これを知った謙信は「戦は刀で行うべきで、民を苦しめるべきではない」と、越後から武田領内へ塩を送ったと言われています。
この行為は、謙信の高潔な人格を物語る逸話として知られており、現在でも「敵の弱みにつけこまず、逆に助ける」ことの例えとして使われています。ただし実際に塩をやりとりした記録は見つかっておらず、史実ではないとされています。
4.伊達政宗「白装束の謁見」
「白装束の謁見」は、出羽国(山形県)と陸奥国(宮城県・福島県)の武将である伊達政宗の逸話です。政宗は奥州の覇者として勢力を広げていましたが、1590年に豊臣秀吉が「小田原攻め」を行った際、出陣の命令に遅れてしまいます。これは「謀反の疑いあり」とされてもおかしくない事態でした。
政宗は責任を痛感し、死を覚悟して白装束(死に装束)を身にまとい、秀吉の前に現れました。その態度に感銘を受けた秀吉は、政宗を赦し、以後も彼を重用したとされています。
現在では、この逸話には根拠がなく、創作だと言われています。しかし、単なる謝罪ではなく、自らの命を担保に「誠意」を示す姿勢は、現代においてもリーダーシップや責任感の象徴として語り継がれています。
5.徳川家康「徳川家康三方ヶ原戦役画像(しかみ像)」
「徳川家康三方ヶ原戦役画像」とは、徳川家康の肖像画です。憔悴したような表情を浮かべていることから「しかみ像」とも呼ばれています。この像は武田信玄と織田信長・徳川家康連合軍が衝突した「三方ヶ原の戦い」で、家康が敗戦した直後の姿を描いたという逸話があります。家康が慢心を戒めるために自身の姿を描かせたという話は、家康らしさを感じさせ、広く知られるようになりました。
現代ではこの話は創作とされており、後世になってから描かれたという説もありますが、家康の慎重さと自己鍛錬の姿勢を象徴する逸話として語り継がれています。
6.武田信玄「信玄堤の築造」
「信玄堤」は、甲斐国(現在の山梨県甲斐市)にある堤防です。武田信玄が築いたとされています。この場所は釜無川と御勅使川の合流点で、たびたび氾濫が起こり、近隣の農地や民家が甚大な被害を受けていました。信玄はこれを重く見て、20年弱かけて堤防を完成させました。信玄が用いた工法は、孫子の兵法を応用したとされ、当時としては画期的なものでした。また信玄は、商人や職人たちを周辺に集めて住まわせたため、まちは大きく発展しました。信玄の優れた内政手腕や発想力を物語る逸話として知られています。
7.毛利元就「三本の矢の教え」
「三本の矢の教え」とは、毛利元就が三人の子どもたちに家族が団結することの重要性を説いた逸話です。元就は晩年、三人の息子(隆元、元春、隆景)を呼び寄せ、それぞれに矢を一本ずつ渡し、折らせました。一本の矢は簡単に折れても、三本束ねると折れにくくなることを示し、「兄弟が力を合わせれば、どんな困難にも打ち勝てる」と教えました。この話は、今でも「団結は力なり」という言葉を象徴する逸話として語られています。
実際に毛利三兄弟は、見事に協力し合い、毛利家を中国地方最大の戦国大名へと成長させました。ただし現在では、元就の書いた「三子教訓状」が元となって創作された逸話だと言われています。
戦国時代にまつわる豆知識

ここでは、戦国時代にまつわる豆知識について、鉄砲・忍者・刀・家紋の4つのカテゴリーにわけて紹介します。
戦国時代の鉄砲の豆知識
日本で最初に鉄砲をつくったのは「刀鍛冶」
1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって、日本に鉄砲が伝来しました。鉄砲を手に入れた島主の種子島時尭は、島の刀鍛冶の頭首・八板金兵衛清定に鉄砲の製造を命じました。金兵衛はすぐに銃形を完成させましたが、銃身と銃底を塞ぐネジ切りに苦戦しました。伝説では、娘の若狭がポルトガル人に嫁いだことでネジの技術を手に入れたとされています。
いずれにしても、金兵衛が国産化を成功させたことで、鉄砲は日本各地に広まり、戦国時代の戦術や勢力図を大きく塗り替える原動力となりました。
堺(大阪)や国友(滋賀)は鉄砲鍛冶のまちとして栄えた
鉄砲が日本に伝来して以来、その製造技術は各地に広まりましたが、なかでも摂津国(現在の大阪府北中部)の堺や近江国(現在の滋賀県)の国友は、鉄砲鍛冶のまちとして大いに栄えました。堺はもともと貿易港として発展していたため、海外の技術や材料の流入に恵まれ、優れた職人が集まる場所でした。一方、国友は織田信長の保護を受け、鉄砲製造地として発展を遂げました。これらのまちは、日本に鉄砲が普及するのを支えた拠点と言えるでしょう。
戦国時代の忍者の豆知識
甲賀は忍者のおかげで現在も製薬会社が多い
滋賀県の甲賀郡は、かつて「甲賀流忍者」と呼ばれる忍者集団が活躍した地です。甲賀郡の山々には多くの薬草が自生していたことから、甲賀流忍者は薬の扱いに長けていました。甲賀流忍術の極意書「萬川集海」には、忍者が自ら薬草を育て加工し、さまざまな薬を生み出していたことが記されています。その流れを受け、現代においても甲賀地域には製薬会社が多く存在し、薬に関する産業が盛んな土地として発展を続けています。
「服部半蔵」は一人ではなかった
「服部半蔵」は、徳川家康に仕えた伊賀流の忍者として有名です。実は「服部半蔵」とは一人の人物を指すものではなく、服部半蔵家の歴代当主の名前です。服部半蔵が活躍したことで有名な「伊賀越え」(家康が「本能寺の変」の後に本領である三河国へ帰還したこと)は、二代目の「服部半蔵正成」による功績です。二代目以降は武士としての役割が強まり、「服部半蔵」は一人の英雄の名から、徳川幕府を支える由緒ある家柄の象徴となりました。
戦国時代の刀の豆知識
戦国時代、戦術の変化により刀も変化した
戦国時代には戦術や戦場の状況が大きく変化し、それに応じて刀の形状や用途も進化しました。それまでは馬に乗って一対一で戦う馬上戦が多く、刀も反りが深く太い「太刀(たち)」が主流でした。しかし戦国時代には合戦の規模が拡大し、集団戦が増えました。そのため歩兵や砲兵の役割が重要となり、より素早く抜けて扱いやすい「打刀(うちがたな)」が主流となります。また、鉄砲の普及によって戦の間合いが広がったことで、刀は主力ではなく補助的な武器としての役割が強まりました。
戦国時代の家紋の豆知識
織田信長は家紋を7つ持っていた
織田信長といえば「織田木瓜(おだもっこう)」の家紋が有名ですが、実は信長は7つもの家紋を使い分けていたとされています。例えば、中国の通貨を用いた「永楽通宝紋」は経済力を象徴し、平氏の家紋である「揚羽蝶紋」は織田家の格式や血筋を示すものだと考えられます。家紋の巧みな使い分けは、信長が権威の演出に長けていた証とも言え、彼のしたたかな知略の一端を物語っています。
徳川家康は朝廷から下賜される家紋を断った
朝廷は、天下統一を成し遂げた徳川家康に「菊紋」「桐紋」の下賜を検討しました。これらの家紋は天皇および皇室を表し、朝廷から賜った場合しか使用できませんでした。しかし家康は、徳川家の象徴である「三つ葉葵紋」を守るため、これらの紋の下賜を辞退しました。それだけではなく、家康は「葵紋」を徳川家以外に使用するのを禁止し、江戸時代には無断使用した者が厳罰の対象となるほどでした。家康の計略により、葵紋は権威の象徴となったのです。
戦国時代を体験できるおすすめのイベント4選
戦国武将の逸話を現代でも体験できるイベント4選を紹介します。
1.万灯会・桶狭間古戦場まつり
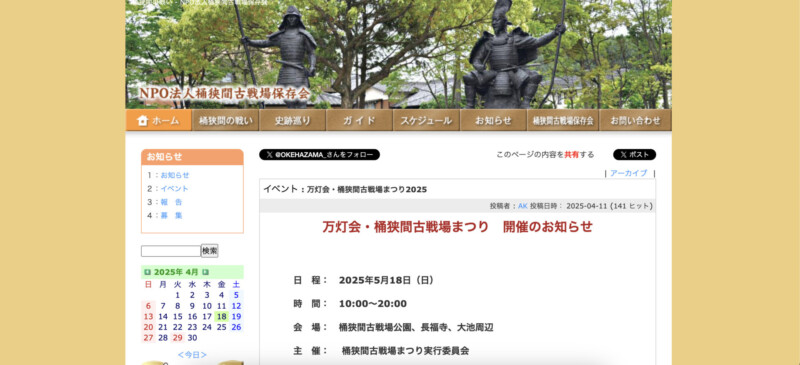
「万灯会・桶狭間古戦場まつり」は、愛知県名古屋市緑区で開催されている祭りです。1560年の「桶狭間の戦い」で命を落とした織田信長・今川義元両軍の戦死者を供養することを目的としています。夕刻から行う「万灯会」では、大池の周辺で3,500本もの灯ろうが点灯されます。また、300名以上が参加する武者行列や合戦再現劇、甲冑試着体験など、戦国時代の雰囲気を体験できる催しも行われます。
イベント概要
- イベント名:万灯会・桶狭間古戦場まつり
- 次回開催日:2025年5月18日(日)
- 開催地:愛知県名古屋市緑区桶狭間北3-1001 桶狭間古戦場公園 他
参照:桶狭間古戦場保存会|名古屋市緑区| – 万灯会・桶狭間古戦場まつり2025
2.すのまた秀吉出世まつり

「すのまた秀吉出世まつり」は、岐阜県大垣市で開催されている祭りです。豊臣秀吉が一夜にして築いたとされる「墨俣一夜城」の伝説にちなみ、出世開運を願います。祭りの目玉は、地元の小・中学生が武将や姫に扮する「武者行列」で、約1.4kmを練り歩きます。またステージイベントでは、墨俣太鼓や武将隊の演舞、大道芸にビンゴゲームなど、さまざまな催しが行われます。会場では「楽市楽座」と銘打った飲食バザーや宝探しクイズも行われ、家族連れで賑わいます。
イベント概要
- イベント名:すのまた秀吉出世まつり
- 次回開催日:2025年10月5日(日)
- 開催地:岐阜県大垣市墨俣町墨俣字城之1742-1 墨俣一夜城址公園一帯
参照:すのまた秀吉出世まつり|イベント|岐阜県観光公式サイト 「岐阜の旅ガイド」
3.仙台・青葉まつり

「仙台・青葉まつり」は、宮城県仙台市で開催される祭りです。1985年、伊達政宗の350回忌にあわせて開催され、今では仙台三大祭りの一つとして親しまれています。祭りは2日間にわたり行われ、初日は軽快な「仙台すずめ踊り」が市内を賑わせます。2日目の「本まつり」で実施される「時代絵巻巡行」では、政宗が率いる甲冑姿の武者隊や鉄砲隊など、戦国絵巻を再現した行列がまちを練り歩き、豪華絢爛な山鉾が巡行します。
イベント概要
- イベント名:仙台・青葉まつり
- 次回開催日:2025年5月17日(土)・18日(日)
- 開催地:宮城県仙台市青葉区桜ケ岡公園1-3 西公園 他
参照:仙台・青葉まつり
4.謙信公祭

「謙信公祭」は、新潟県上越市で開催されている祭りです。上杉謙信の遺徳と武勇を称えることを目的としています。見どころは、鎧兜を身につけ槍刀を持った武者たちが練り歩く「出陣行列」と、かがり火のなかで上杉・武田両軍が戦いを繰り広げる「川中島合戦の再現」です。2025年の第100回謙信公祭では、謙信役として俳優・歌手の松平健さんが出演予定です。他にも「謙信公みこし巡行」や古式砲術の披露、殺陣のパフォーマンスなどが行われ、まるで戦国時代にタイムスリップしたような気分を味わえるでしょう。
イベント概要
- イベント名:謙信公祭
- 次回開催日:2025年8月23日(土)・24日(日)
- 開催地:新潟県上越市中屋敷 春日山城跡周辺
参照:謙信公祭とは | 謙信公祭 | 【公式】上越観光Navi – 歴史と自然に出会うまち、新潟県上越市公式観光情報サイト
戦国時代を体験できるおすすめのスポット3選
ここでは、戦国時代の逸話を体験できるスポット3選を紹介します。
1.岡崎城公園「しかみ像」(愛知県岡崎市)

「しかみ像」は、愛知県岡崎市の「岡崎城公園」にある像です。この像は「徳川家康三方ヶ原戦役画像」を基に制作されました。2007年、徳川宗家18代当主・德川恒孝氏から岡崎市に寄贈され、公園内の「三河武士のやかた家康館」の南側に設置されました。德川氏は、像の設置時に「強いばかりでなく負け戦をステップに次へ進んでいったことを表す像です」と挨拶しました。
基本情報
- スポット名:しかみ像
- 所在地:愛知県岡崎市康生町561-1
- アクセス:名鉄「東岡崎駅」徒歩15分
- 公式サイト:しかみ像|見どころ・施設紹介|岡崎城公園|岡崎おでかけナビ – 岡崎市観光協会公式サイト
2.信玄堤(山梨県甲斐市)

「信玄堤」は、山梨県甲斐市竜王にある治水施設で、武田信玄が築いたとされています。現代でも一部が残されており、その姿からは信玄の先見性と知恵を伺うことができます。隣接する信玄堤公園では、四季折々の自然を楽しめます。また毎年春には甲州三大御幸祭のひとつ「おみゆきさん」が開催されており、近隣住民に親しまれています。
基本情報
- スポット名:信玄堤
- 所在地:山梨県甲斐市竜王
- アクセス:JR中央線「竜王駅」徒歩で25分
- 公式サイト:信玄堤/富士の国やまなし観光ネット 山梨県公式観光情報
3.郡山城跡(広島県安芸高田市)

郡山城跡は、広島県安芸高田市にある山城跡で、戦国武将・毛利元就が居城とした場所です。元就はこの地で、わずかな勢力から中国地方を制覇する大名へと成長しました。当初は小規模な城であった郡山城ですが、毛利氏の勢力拡大とともに拡張され、巨大な城郭となりました。現在でも山城としての遺構がよく残っています。
基本情報
- スポット名:郡山城跡
- 所在地:広島県安芸高田市吉田町吉田郡山
- アクセス:JR芸備線「向原駅」からタクシー20分
- 公式サイト:郡山城跡(吉田町) | 安芸高田市
【戦国イベントを開催する方向け】戦国時代を体験できるおすすめのアクティビティ4選
ここでは、戦国イベントを開催する予定の方向けに、戦国時代を体験できるおすすめのアクティビティ4選を紹介します。
1.チャンバラ合戦

「チャンバラ合戦」は、スポンジ製の刀を使い、相手の腕に巻かれた「命」と呼ばれるボールを狙って戦うアクティビティです。参加者は戦国武将になったかのような臨場感を味わえます。
ルールがシンプルで、体力や年齢を問わず参加できるため、初めてでもすぐに楽しめます。チーム戦で戦略を立てる面白さもあり、参加者同士の交流が深まります。歴史に興味がある方はもちろん、非日常を体験したい方にもおすすめです。
2.戦国ワークショップ

「戦国ワークショップ」は、戦国気分を味わえる10種類以上のオリジナルワークショップです。戦国時代の文化を体験できます。
戦国武将の象徴ともいえる「家紋」に関するワークショップも複数あり、「オリジナル侍缶バッジづくり」は、好きな武将の家紋やオリジナルの家紋をバッジにできます。「ふぇいすぺいんと顔処」では家紋や和柄を顔や腕にペイントでき、戦国イベントらしい雰囲気を盛り上げます。
3.水合戦-WaterBattle-

「水合戦-WaterBattle-」は、水鉄砲を使って、敵が胸につけた「魂」と呼ばれるターゲットを狙うアクティビティです。まるで戦国時代の鉄砲隊になったような気分を味わえます。
水を使うため暑い季節にぴったりで、子どもから大人まで白熱します。どこで実施しても満員御礼になることが多い、人気のイベントです。
4.忍者合戦 -SHINOBI-

「忍者合戦 -SHINOBI-」は、忍者になりきってチャンバラ合戦をしたり、自軍に与えられたミッションをクリアしたりするアクティビティです。裏切り合戦や巻物争奪戦、手裏剣バトルなど、忍者ならではの特殊なミッションを実施することもできます。非日常のスリルと戦国ロマンを味わう貴重な体験を提供できます。
まとめ

戦国武将の逸話や戦国時代の豆知識を知ると、戦国イベントや歴史スポット巡りがより楽しくなります。かつての合戦を再現したイベントや歴史ある祭り、城・史跡を訪れることで、教科書では味わえない戦国時代の息吹を感じられるでしょう。ぜひこの記事を参考に、戦国武将たちの世界へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。